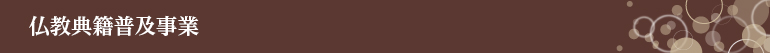
仏教とは、ブッダ(釈尊・お釈迦さま)が35歳のときにさとりを開き、80歳で入滅(死去)されるまでの45年間の説法をもととする宗教です。ブッダは人間の平等を強く主張し、誰もが等しく理解できるよう、それぞれの人に応じて教えを説かれたため、その教えの量は膨大なものとなりました。 「お経」というのは、ブッダが亡くなった後、その教えの言葉を記憶していた弟子たちが集まり、後の世に教えを正しく残すために書かれた仏典(仏教の聖典)群を指します。古代インドの言葉で書かれた沢山の「お経」は、仏教の伝播とともに様々なルートでいろいろなことばに訳されながら多くの国々に弘まっていきました。 中国では、後漢時代から北宋時代にわたって多くの仏典(「お経」)が翻訳(漢訳)されてきました。そうした経典に、中国の高僧の著述を含め、まとめたものが「大蔵経(だいぞうきょう)」と呼ばれる経典の集大成です。
ブッダ(仏陀=目覚めた人の意)が説いた真実の教えを解りやすく伝えるため、さまざまな「お経」の中から、教えの大切な要素とたとえ話を選び、それらを現代語訳し、日常のやさしいことばにかえてまとめたものが『仏教聖典』です。
仏教伝道協会ではこの『仏教聖典』をさらに英語、フランス語、ドイツ語、中国語をはじめ、46の言語に翻訳刊行しています。
この『仏教聖典』を弘めることによって、仏教を全世界の人びとに伝え、争いと憎しみのない平和な社会の実現に少しでも役立ちたいと願い、ホテル・学校・病院等への頒布活動などを行っています。
『仏教聖典』について、詳しくはこちらをご覧ください。
https://bdk-seiten.com/scripture.php(日本語ページ)
https://bdk-seiten.com/scripture.php?lang=en(英語ページ)
また、各国語PDF版『仏教聖典』のダウンロードが可能です。
https://bdk-seiten.com/scripture-download.php(日本語ページ)
https://bdk-seiten.com/scripture-download.php?lang=en(英語ページ)
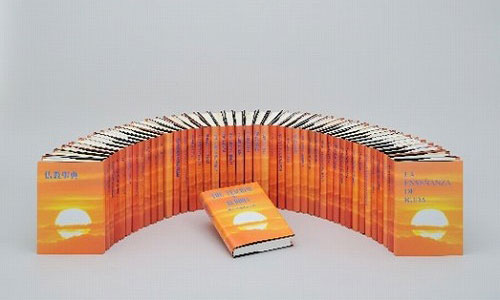
仏教伝道協会では、1982年より沼田惠範の発願により、漢文で書かれた『大正新脩大蔵経』の英訳編纂を進めてきました。『大正新脩大蔵経』全100巻は、大正から昭和にかけて日本の仏教者が一致協力して編集し、日本で出版されたもので、11,970巻・3,360部の経(ブッダが説いた仏典)・律(戒律と教団の規則)・論(経典の解説書や教義書)・疏(注釈)等の聖典が収められています。
この事業では、『大正新脩大蔵経』全ての英訳を目指していますが、まず第一期分として全体量の約10分の1に相当する139の典籍を選択して英訳、出版・データ公開を進めています。
英訳大蔵経事業について、詳しくはこちらをご覧ください。
https://bdk-seiten.com/eiyaku.php(日本語ページ)
https://bdk-seiten.com/eiyaku.php?lang=en(英語ページ)
仏教伝道協会では、世界中の方がたに「英訳大蔵経」をご覧いただくために、出版事業と並行して英訳テキストをインターネット上で公開。協会ホームページを通してPDF 版を配布しています。英訳大蔵経PDF版のダウンロードはこちら。
https://www.bdkamerica.org/tripitaka-list/(BDK Americaのページへリンク)
また大蔵経テキストデータベース研究会(SAT)と共同で『BDK Daizokyo Text Database』を公開し、大蔵経の普及事業を進めています。ここでは、大蔵経英訳事業の成果をWEB上で利用することが出来ます。一部の英訳を閲覧出来るだけではなく 英訳大蔵経と大正新脩大蔵経との文章単位での照合や仏教デジタル辞典を参照することが出来ます。
大蔵経テキストデータベース研究会(SAT)のページはこちら。
https://21dzk.l.u-tokyo.ac.jp/BDK/bdk_search.php

より多くのかたに仏教の精神、文化に触れていただき、心豊かな生活を育んでいただけるよう、寺院や学校などで教材として活用いただける書籍や、幼児向けの絵本、児童向けの仏教まんが、仏教や古今の名言を掲載したカレンダーなど各種仏教関連書籍を出版、頒布しています。